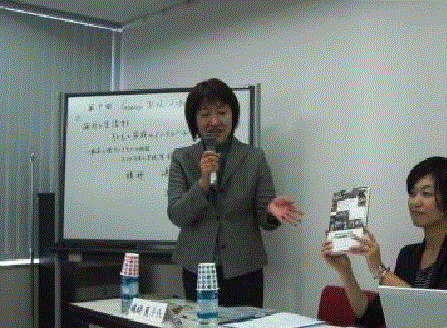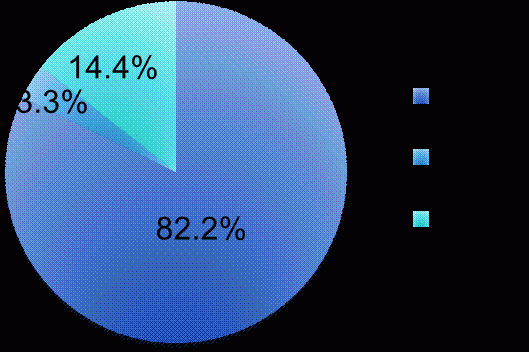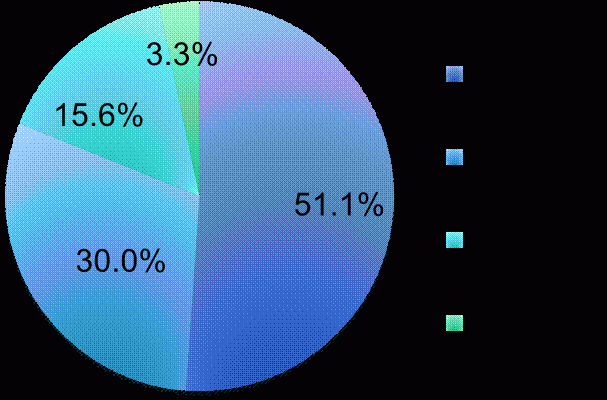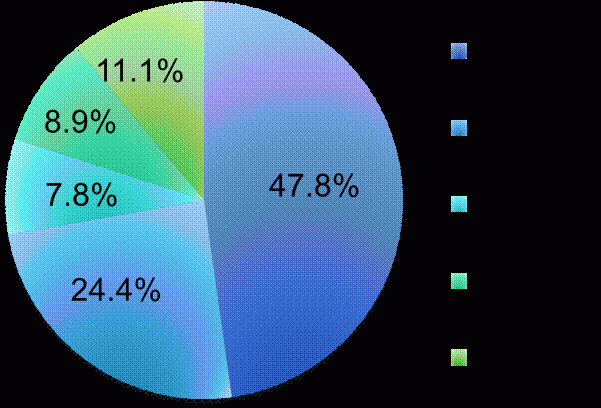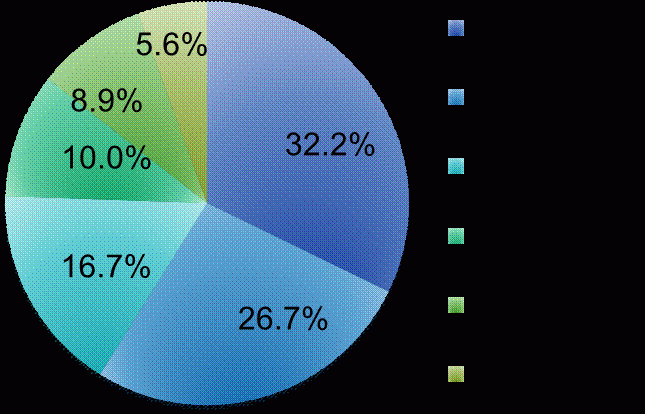以下、嶋崎さん:
With Kidsは海外で生活する子どもたちのメンタルヘルスをサポートする臨床心理士のボランティアグループです。
最初に海外で生活する日本人の状況についてお話しさせていただきます。
<海外で生活する子どもたち>
海外に3ヶ月以上滞在する日本人
・1980年の約42万人から増加し続け、118万人を越える(2011年10月1日現在)
・そのうち義務教育期の子ども(小学生・中学生) 6万4950人(2011年4月15日現在)
(2012年10月外務省発表)
→ 0歳から18歳の子どもは10万人を超えると推定される
就学の状況
日本人学校で学ぶ子どもは全体の3割程度 。あとの7割は現地校、国際学校で学ぶ。
アジア地域では、日本人学校に就学する割合が高い。
・日本人学校の設置状況
51カ国・地域に88校。約1万9千人が学ぶ
・補習授業校の設置状況
56カ国・地域に203校。約1万7千人が学ぶ
(2011年4月15日現在)
文部科学省HPより
<海外生活者のメンタルヘルスサポート>
・心の問題は、“日本語(母語)による介入自体が治療的”だが、日本語でサービスを受けられる都市・国は限られる
“海外は大多数の邦人にとって精神医療過疎地域”(外務省メンタルヘルス対策上席専門官 鈴木 満 氏)
・
「日本語で受けられる海外のこころの相談機関・窓口」 =毎年更新されているGroup Withのリストは貴重な情報源! 掲載国(2012年):アメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ベルギー・オランダ・スイス・スウェーデン・ドイツ・オーストラリア・シンガポール・タイ・インドネシア・ベトナム・中国・韓国
Group Withの「日本語で受けられる海外メンタル相談機関・窓口」リストを見ても日本語で相談が受けられる国と地域は限られていることが分かります。
<子どもたちのメンタルヘルスサポート>
・日本人学校(学齢期の子どもの約3割が通う)
スクールカウンセラーの配置は極めて限られる
(文部科学省からの派遣はなし)
*大規模日本人学校では現地採用のカウンセラーが配置されているところもあります。
・現地校・国際学校
スクールカウンセラーが配置されていても、
日本語で相談できるわけではない
日本国内だったら
・スクールカウンセラーの配置
1995年から文部科学省の取り組みがスタート
現在:全国の公立中学校の87%にスクールカウンセラー配置
(東京都は2003年度から全校配置)
小学校、高校への配置も順次進められている。
・0歳から18歳を対象に多様なサポートのリソースがある
例えば・・・
保健所 乳幼児健診(3ヶ月、1歳半、3歳の3回は公費負担)
教育センター 教育相談
児童相談所 心理相談
学生ボランティアによる家庭訪問、学校生活支援
スクールカウンセラーの役割
・児童生徒に対する相談・助言
・保護者や教職員に対する相談(カウンセリング、コンサルテーション)
・校内会議等への参加
・ 教職員や児童生徒への研修や講話
・相談者への心理的な見立てや対応
・ストレス・チェックやストレス・マネジメント等の予防的対応
・事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケア
(文部科学省HPより )
1990年代にいじめや不登校など心の問題への意識が高まり、文科省の取り組みがスタートしました。スクールカウンセラーは学校の教育相談の体制に大きな役割を果たしています。
<With Kids 概要>
・「海外で暮らす子どもも国内と同じようにメンタルヘルスのサポートを受けられたら・・・」という思いから生まれた。
・臨床心理士のボランティアグループ
・2006年4月に設立
・メンバーは約15名
・スクールカウンセラーなどの教育分野の他、医療、福祉、産業の各分野で、臨床心理士として勤務する傍ら、With Kidsのボランティア活動に参加
・半数近くが海外滞在や海外での子育てを経験しており、現在海外で生活しているメンバーも数名(中国2名、ロンドン、シカゴ、ジャカルタ各1名)
0歳から18歳まで、日本国内に住んでいる子どもには国や自治体から様々なサポートがありますが、そういったサポートは海外ではほとんど受けることができません。海外で暮らす子ども達も日本と同じようにサポートが受けられたらという思いから私たちの活動が生まれました。
代表の澤谷厚子は夫に帯同して1995年から2003年までインドネシアのジャカルタに生活し、その間に現地在住の日本人のメンタルヘルスケアを目的としてボランティアグループ「ジャカルタカウンセリング」を立ち上げました。2003年GroupWithの第1回セミナーでその体験をお話したという経緯があります。
その頃日本では子どもたちの心の問題に関心が高まり、スクールカウンセラーの配置が急速に進められていました。帰国後、澤谷もスクールカウンセラーとして子どもたちと係わる中で、海外で暮らす子どもたちにも同じようなサポートが必要という思いを「海外生活経験のある臨床心理士の仲間」と共有したことがきっかけとなって、2006年の4月にWith Kidsを立ち上げました。
<With Kidsの活動>
1. メール相談
2. 日本人学校等の訪問活動
3. 一時帰国時の受診サポート
1.メール相談
(1)受付の方法
受付メールアドレス: soudan@withkids-kaigai.com に、
件名:相談(海外)として「空メール」(本文なし)をご送信
ください。
↓
当会から「相談受付フォーム」をお送りします。
必要事項と相談内容をご記入の上、ご返信ください。
↓
1週間以内に回答メールをお送りします。
・相談は無料。匿名の相談も可。守秘義務を遵守します。
・1回の相談はメール3往復を一区切りとさせていただいています。
*海外在住者からの日本語での相談をお受けしています。
受付の方法 その2
※ホームページからもご相談を受け付けています。
新しいホームページ
http://www.withkids-kaigai.com/ メールアドレス(相談受付)も変わりました
soudan@withkids-kaigai.com
*KDDIの助成を受け、ホームページをリニューアルしました。yahoo mailから新アドレスに変更したため中国からのアクセスも可能になりました。
(2)メール相談の利点と難しさ
利点
簡便性:
・どこからでも(インターネット利用可能であれば)
いつでも(24時間)
→ 距離や時差が障害にならない
匿名性: 実名を知らせないでも相談できる
→ 狭いコミュニティでも知られる心配がない
書くことそれ自体の意味
→ 言葉にし、意識化することで、気持ちや考えを整理
難しさ
<相談者にとって>
・すぐに返答が返ってこない
<回答者にとって>
・情報が少ない → アセスメント、共感の困難さ
・質問ができない(一方向コミュニケーション)
・非言語的な情報が得られない(相談者の表情、しぐさ、声のトーンなど)
・対象となる子どもの行動観察ができない
・回答がどう受け止められたか、返信が来なければわからない
メール相談には以上のような難しさはありますが、他の方法が少ない海外では意味があると考えています。
どんな相談であれ、日本を離れて慣れない土地で子育てをしていることへのねぎらいや、不安な気持ちを受け止めるというところから始めます。お子さんの相談に関しては診断やアセスメントをするのではなく、まず今その場でお子さんに対してどのような関わりができるのかという具体的なアドバイスをするように心掛けています。
アジアからの相談が多いのは、近年日本企業の進出が急増しているためだと考えます。外務省の発表によると、就学年齢の子どもの滞在者数は中国が最多となっています。滞在者の総数では北米が最多なのですが、グラフで見るとアメリカからの相談は少なくなっています。その理由として、現地での子育てサービスが充実していること、第一言語が英語であり、日本人にとっては相談の際の言葉の壁が低いことが関係しているのかもしれません。
また、With Kidsは海外日本人学校への訪問を行っていますが、これまでアメリカには行っていないこともあり、With Kidsの活動が周知されていないということも考えられます。
グラフ3. 相談対象者の年齢
グラフ4の相談内容の中で「発達」に分類されるのは、「言葉に遅れがある」、「発達障害と診断されたが、どのように関わればよいか」といった相談です。「性格・行動」の中にも「性格・行動」に分類していますが、その背後にも発達障害がある可能性があります。
「発達」に入るものが相当数あると思われます。(「かんしゃくが激しい」「注意しても伝わらない」など)
また、発達障害かどうかはわかりませんが、国内では「通常学級に在籍していて、知的には問題ないが学習に著しい困難を示す子ども」が6.3パーセントいると言われています。したがって、海外でも同様にそういった子どもが100人中5人から6人はいると推測できます。
主な相談テーマ <就学前>
・かんしゃくが激しい
・注意しても伝わらない
・友だちを叩いたり、モノを投げたりする
・自分の頭を床や壁にぶつける(自傷)
・緊張すると舌を出す(チックかどうか?)
・何でも噛むクセ
・言葉の遅れ(単語は出るが文にならない)
・幼稚園で言葉を発しない
・集団遊びに加わることができない
・同じ場所に座っていることができない
・特定の服しか着ようとしない(こだわり)
・子どもを叩いてしまう(子育てストレス)
・子どもとうまく関われない
・母親のうつ症状
・何語での療育が良いか
・英語ができなくても受けられる発達検査があるか
・一時帰国時の受診機関の情報
「幼稚園で言葉を発しない」ということで場面緘黙症ではないかとの相談がありました。ネットで調べてかえって不安が高まってこちらに相談するケースもあります。
主な相談テーマ <小学生>
・発達障害(LD、ADHD、自閉症など)の懸念
・爪噛みをやめさせたい
・吃音
・滑舌の悪さについて
・いじめの加害者になった
・いじめ被害に対する学校側の対応
・友人との関係
・社会性が身についていない
・家族に対してだけキレる
・暴言が著しい
・自傷・他害のために授業に参加できない
・頭痛や吐き気で登校できない
・男の先生が怖くて登校できない
・学校でお漏らしをしてしまう
・特別支援学級に受け入れ困難と言われた
・帰国予定地域での特別支援学級の状況
主な相談テーマ <中学生>
・親子関係(娘が父親と口を聞かない)
・不登校
・アスペルガー障害(無気力、帰国すべきか)
・自閉傾向の子どもの帰国後の転入
・摂食障害
・学習の遅れ
・学習意欲がない
主な相談テーマ <高校生>
・子どもの生活態度と親の関わり方
・国際学校への不登校
・日本人カウンセラーを探している
発達の相談がなくなり、また相談自体も少なくなります。
中高生では、相談件数そのものが少なくなります。これは、子どもが中高生くらいになると、母親が育児経験を重ねて自分なりの解決方法を見つけられるようになっていたり、また、進路のために母子のみで帰国するケースが増えるためだと思われます。したがって、発達障害については、既に診断がついており、帰国後の適応を視野に入れたご相談が多くなります。また、日本人学校は中学校までなので、高校生の場合はインターナショナルスクールや現地校に通っているということになります。
<発達障害とは>
・自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害
・学習障害
・注意欠陥多動性障害
その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの
・広汎性発達障害
自閉症を中心とした、近接の自閉的障害の一群。社会性やコミュニケーション、想像力の障害とそれに基づく行動の障害を特徴とする。
・学習障害
基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すもの
・注意欠陥/多動性障害(ADHD)
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの
発達障害を持つ子どもへの理解
子どもの状態像を正しく把握し、理解する
・子どもができることは?
・子ども自身が困っていることは?
・子どもが苦手なことは?
→「治療」ではなく「対応」を考える
日本国内では、2007年から「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられている
以下、嶋崎さん:
2. 日本人学校等への訪問活動
(1) グループによる訪問
個別相談、座談会、ワークショップ等を目的
2007年以降、延べ11回実施
4ヵ国: インドネシア(6回)・台湾(3回)・韓国・中国
9 都市: ジャカルタ・バリ・台北・高雄・台南・台中 ・ソウル・北京・天津
(2)個々のメンバーによる訪問
視察、広報、コンサルテーション、幼児健診支援など
・13ヵ国(19都市):
タイ(バンコク)、スリランカ(コロンボ)ドイツ(ベルリン、デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン)イタリア(ローマ、ミラノ)、フランス(パリ)、イギリス(ロンドン) スイス(チューリッヒ)、オーストリア(ウィーン)オランダ(アムステルダム)、ベルギー(ブラッセル)チェコ(プラハ)、スペイン(マドリッド)、北米(ローリー)
訪問活動は、日本国内に住んでいたら受けられるような様々なサービスを出前でやってみようという試みです。
代表の澤谷がジャカルタ滞在中にジャカルタカウンセリングというグループを立ち上げ活動をしていたこと、澤谷を含むメンバーの4名がジャカルタ滞在経験者だったことから、海外訪問は、2007年のジャカルタ訪問からスタートしました。毎年訪問し、乳幼児健診の発達検査のお手伝い、日本人学校での個別相談会、講演会、子育てワークショップなどを行ってきました。
日本人学校訪問は国内での勤務の合間に行うため、現地滞在は2,3日に限られます。個別相談も1回で終わるのでメール相談でのアフターケアが必要になってきます。この活動は海外に住む人へのサービスということもありますが、実際に現場を見に行くという点でも私たちの活動にとって大きな意味があります。メール相談は顔が見えないため躊躇なさる方もありますが、直接お会いすることによってその後その地域からの相談が増えることにも繋がります。
今年度の訪問活動
・2012年10月5日から8日 台湾(台北・高雄・台南・台中)
・2013年2月中旬(予定) インドネシア(ジャカルタ)
今年度の台湾での活動
・参加スタッフ 4名
・個別相談24件、座談会2回、講演会2回
・CAREワークショップ2回 実施
・1日目 午後 台北日本人学校訪問
講演会:発達障害 1.保護者向け 2.教師向け
・2日目 午前 高雄日本人学校訪問 個別相談
午後 CAREワークショップ
座談会:思春期(保護者向け)
・3日目 午前 台南 個別相談
座談会:思春期(保護者向け)
午後 台中 個別相談とCAREワークショップ
・4日目 午前 台中日本人学校を訪問(教頭先生)
台湾は、木下が台湾滞在中の2007年に、現地で国際結婚した女性の会でWith Kidsの活動を紹介したことがきっかけとなってその後現地からオファーがくるようになり、今年3回目の訪問をしました。
タイトなスケジュールの中で実施できるのも現地にきちんとした受け入れ体制ができているからだと思います。突然日本人学校にこういうグループで訪問したいと言ってもなかなかできるものではありません。回数を重ねて信頼関係ができ、受け入れてくださるグループや団体ができてくるうちに、こういったかなり密度の濃い活動もできるようになりました。もう少し回数や国数も増やしたいのですが、資金面はほとんど自費で行っているので、なかなか厳しい状況です。今年度の台湾訪問は現地での交通費は受け入れ側が出してくれて、来年のジャカルタ訪問はKDDIさんの助成金で交通費が出ることになっています。今後少しずつ財源の確保が必要になってくると思います。
日本人学校等へ提供可能なプログラム
・児童・生徒本人、保護者、教職員との個別面接 (相談、コンサルテーション)
・児童・生徒の行動観察や簡易発達検査によるアセスメント
・幼児健診の支援
・事例検討会
・講演会や研修会、参加型ワークショップ
講演会や研修会、参加型ワークショップのテーマ
<教職員向け>
・発達障害、精神病理、メンタルヘルス等
・教室で使えるグループワーク
<保護者向け>
・発達、思春期の問題
・CAREワークショップ(ペアレント・トレーニング)
・Common Sense Parenting(CSP) の普及版(児童)と幼児版
・海外生活でのストレスマネージメント、リラクゼーション等の研修会
<児童・生徒向け>
・心の健康教育
・SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)
教職員向け:海外では研修の機会が限られるので、発達障害やメンタルヘルスに関する講演会を行います。
保護者向け:子どもとの関わりを悩んでいるケースが多いので、「どうしたら子どもと良い関係をつくっていけるか、どのように言えば言うことを聞いてくれるか」といったペアレントトレーニングなどのワークショップを提供しています。
児童生徒向け:日本国内で行われているプログラムを先生方をサポートする形で実施することができます。
提供できる2種類のワークショップ
(1) Careとは?
Child-Adult Relationship Enhancement
-子どもと大人のきずなを深めるプログラム-
・米国オハイオ州シンシナティ子ども病院で開発された、子どもと関わるすべての大人のための心理教育的介入プログラム。
・子どもとのより良い関係を築くために大切なことを、ロールプレイを用いながら体験的に楽しく学んでいく。
・子どもが言うことをきけるよう、適切で効果的な指示の出し方も学ぶ。
http://www.care-japan.org/トレーニングを受けたメンバーがトレーナーとして実施できるような体制を整えつつあります。
(2) Common Sense Parenting(CSP)とは?
・心理学の行動療法の理論背景を基に、子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を効果的にしつけられるスキルの体得を経験的に学習するプログラムです。(「CSPトレーニング・マニュアル」より)
全米最大の児童養護施設であるガールズ・アンド・ボーイズタウンで開発されたものを日本用に改訂した普及版(児童用)の他に、幼児用もある。
メンバーの何人かが研修会に参加して、勉強を始めたところです。
3. 一時帰国時の受診サポート
・発達障害の疑い
→診断には、日本語による検査実施、受診が欠かせない。
・日本国内でも発達障害を専門に診る児童精神科医はまだ少なく、初診まで数ヶ月待ちの場合もある。
・限られた一時帰国期間中に予約から受診までを行うことがむずかしい場合もある。
☆With Kidsでは専門医と連携し、申し込みから初診までスムーズに進められるように、情報提供や予約支援を行っています。
海外では日本と同じように幼児検診を受けられないことから、言葉の遅れの心配を抱える人が多いという状況があります。
事例:
「3歳9ヶ月になっても単語は出てくるが2語以上の文章が出てこない。心配を抱えているものの、誰にも相談できないという相談。お子さんに会って見ると言葉だけではなくいろいろな面で心配な様子が見られた。一時帰国も近いので、そのお母さんは帰省先の地元の自治体に電話をして相談を申し込んだのだが、「00ヶ月待ち」と言われたり、「海外に住んでいるのでは手遅れになる」というようなことを言われたようで、絶望的な気持ちで電話をしてきた。言葉の遅れ、自閉症(そのお子さんは自閉症だったので)に詳しいメンバーに相談し、滞在先に近く、できるだけ早く受診できるところを幾つか候補を挙げてもらった。そういった病院に行くことへの不安や、大きい病院がいいのか小さいクリニックがいいのかという希望も聞きつつご紹介をした。発達検査や診断は一回の受診でできるわけではなく通常4回ほどかかり、初診から診断が下るまで1ヶ月程度は必要であるということも説明した。」
受診のために一時帰国をした場合、大事なことは、診断名だけを持って赴任国に戻るのでは、ご家族になって何の支えにもならないということです。赴任国で日本語のサポートも受けられないまま、子どもをどのように見守ったらいいのかという不安な気持ちだけを抱えて過ごすことになりかねません。診断を受けたなら、家庭がどのようにその子に関わればよいのかというアドバイスや指導まで受けた上で、赴任国に戻ることが理想です。この事例のお子さんの場合は、クリニックで診断を受けつつ、並行して小さなプライベートの相談室で家庭でできることの訓練を何度か受けて戻ることができました。
日本国内にいれば、居住地の自治体が行う発達相談や発達検査、療育指導などを受けられますが、一時帰国中で住民票がなければそのようなサービスを利用できません。そのため、住民票がなくても受けられる相談機関を探す必要が出てきますが、With Kidsで受けたメール相談の中で帰国しての受診が必要になる場合はできる限りのサポートをしていきたいと思っています。そういう事情に理解のある児童精神科医や相談機関の情報を常に集めているという状況です。
<海外で生活する子どもと家族のメンタルヘルス(補足)>
☆ 相互に影響しあう家族のメンタルヘルス
<子ども>
帯同についての思い(納得できていなくても、赴任の前に話し合いがあったか)
何語で教育を受けるか(年齢、滞在年数、進路)
親への依存度 高い(移動、遊び場、友だちの選択など)
<母親(妻)>
日本でもっていたキャリアや趣味の分断
日本であったソーシャルサポート(実家、友人、地域)を失う
人間関係や活動を一から築かなければならない
子どもに関心が集中 思春期の場合はマイナスも・・・
夫の理解、サポートが得られるか
流産や不妊 (狭くて均質なコミュニティでの二次受傷も)
子どものサポートをするからと言って、子どもだけを見ていては問題が見えてきません。家族の中のメンタルヘルスはお互いが影響し合っています。
子どものことで相談を受けた時、メールをやり取りするとお母さん自身のストレスや不安だったりすることが多々あります。明示的に表れるテーマの裏側に色々なストレスが見えてきます。
海外では安全面の問題もあり、どうしても親への依存度が高くなりますが、子ども、特に思春期の子どもは親との距離感が近過ぎて息苦しくなることもあります。
夫の海外赴任に際して、新しい環境への適応という点では、夫も妻も同じですが、職場という所属のある夫と違い、妻は、新しい場所で一から、人とのつながりや生活を築いていかなければならない場合が少なくありません。「戸惑いや悩みを話せる場」や「生き甲斐」がなく、子どもに関心が集中しがちになるとマイナスの影響が出てきます。母親が一人で子育てに悩むケースもよく見られます。
これまで支援、サポートが殆ど入っていないと思われる分野として、海外で流産や不妊といった問題に直面したときの駐在員妻のストレスがあります。均質で狭い日本人コミュニティの中で、国内にいるときよりもより強い疎外感を感じたり、流産や不妊に対する何気ない一言で傷つきます。子どもがいるのが当たり前というコミュニティには入りにくいということもあります。こういうことを相談できる場というのは殆どないのではないでしょうか。
ここまでは駐在員の家族のストレスを紹介しましたが、国際結婚で長期に滞在する日本人女性からの相談も受けることがあります。
以下、木下さん:
台湾での相談
台湾には、台湾人と結婚している日本人がとても多くいらっしゃいます。歴史的な背景もありますが、欧米への留学中に台湾人と出会い、結婚してそのまま台湾に暮らすというケースも多いようです。したがって、未就学児の場合は言葉に関するご相談がよくありました。家庭では、北京語、台湾語がメインで、母親は日本語、また夫婦共通の言語として英語が加わる場合もあります。そこで、前述したように、言葉の遅れが言語環境なのか発達の遅れによるものなのかどうかわかりにくいことがあります。家族をとても大切にするのですが、義両親やご主人とは文化差による養育方針の違いから、母親がストレスを感じることもあるようです。どちらかと言うと親日的ではありますが、授業で反日的なことを教えられるとその前後にいじめがあったという話も聞きました。
また、中高生になるとアイデンティティの問題も出てきます。中学校までは日本人学校でその先は現地の高校に通うとなると言葉の問題も出てきます。現地校は宿題の量も多く、朝7時から夜7時まで授業という話も聞くほどで、小学校から通うお子さんも大変ですが、高校からいきなりそのような環境に通う場合も大変です。
訪問時に受けた個別相談では、両親で言っていることが違うということで悩んでの相談もありました。また18歳から35歳の間に1年から2年兵役に行かなければならないので、そこで新たに自分の国籍を考え直すお子さんから相談を受けることもありました。
以下、嶋崎さん:
<今後に向けて >
1.メール相談
相談者が安心して相談できるウェブ環境を整える
→KDDI財団の助成金を得て、ホームページを改訂
2.日本人学校等の訪問活動
→より安定的な活動のためには財源の確保が課題
3.一時帰国時の受診サポート
→海外生活者への理解があり、協力を得られる医師、医療機関等のネットワークづくり
勤務の合間に志だけはあって続いている活動ですが、現地でサポートを必要としている人がいるかぎり、一人一人のメンバーができることを続けていきたいという思いがあります。
海外では学校の先生へのサポートが少ないと実感しています。国内では自治体など第三者からの支援も考えられますが、海外では狭い社会の中で問題解決をしなければなりません。
以前、知的に遅れが見られるお子さんのご家族が、事前に学校側に相談することなく、日本人学校への入学を希望されたケースがありました。すでに家族で赴任してしまって、受け入れざるを得ない状況でしたが、先生の数が限られる中、本人の安全確保や他のお子さんの学習に支障が出るなどの問題になりました。お子さんの遅れについての認識が学校側と保護者の側で異なり、保護者の協力を得にくい状況で学校側が苦慮していました。現地に在住していたWith Kidsのスタッフ(臨床心理士)が第三者として間に入り、改善策を見出したということがありました。先生と保護者が一対一だと解決の糸口を見つけるのが難しい場合でも、誰かが入るとスムーズに運ぶことがあります。そのような、第三者としてのサポートができるのではと考えています。